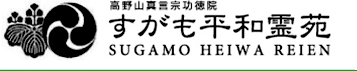 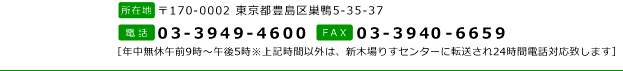 | |
能登半島地震で幕を開けた令和六年 も、終わりに近づいています。豪雨災 害にも追い打ちをかけられ、今なおご 苦労されている被災地の皆さまに心よ りお見舞い申し上げます。 私たちは、災害や老病死など苦難の 経験から、どんなに祈っても願いが叶 わないことがあると知り、「どうせ無 理だ」と諦めの言葉を口にすることが あります。しかし、私たちの心には本 来、無限の可能性が秘められているの です。 先日、どうしても子供たちに見せた いと思い立ち、福島県いわき市の「ハ ワイアンズ(旧常磐ハワイアンセンタ ー)」を訪れました。 高度経済成長期、かつて炭鉱の町と して栄えたこの地は、石油エネルギー の台頭により炭鉱が閉鎖され、深刻な 経済危機に直面しました。そんな中、 町の人々は豊富な温泉資源を活かし、 新たな観光施設を作るという挑戦を始 めました。それがハワイアンズの産声 です。「こんな寒い炭鉱の町にハワイ なんて作れるはずがない。」多くの人 がそう嘲笑する中、当初、一握りの人 々が抱いた信念は、やがて多くの人々 の心を動かしていきました。特に象徴 的なのが、炭鉱の娘たちによるフラダ ンスショーです。未経験だった彼女た ちは厳しい稽古を重ね、その努力は観 光の中核を担うまでに結実しただけで なく、女性の新しい生きかたを示し、 逆境に立ち向かう希望の象徴にさえな ったのです。 ハワイアンズ創設のエピソードは、 『フラガール』という映画を通じて全 国に広まりました。その後も東日本大 震災をはじめ、幾多の困難に見舞われ ながらも、世の変化に向き合い続け、 今なお多くの観光客を迎えています。 人生は短い――。しかし、ひとたび 宿した一念は、時に無限大の結果を生 む可能性を秘めています。そんな一念 のことを、仏教では本来だれにでも平 等に備わっている「仏性」と呼び、こ れに気付くことの大切さを説いていま す。 来る年頭祈願には、皆さまの一念を 仏さまにお届けし、その思いが花開く よすがとなりますよう、謹んでご案内 申し上げます。 功徳院 住職 松島龍戒
お盆の季節は過ぎても、まだまだ猛暑が続きますが、皆さまにはご平穏でお過ごしのこととお慶び申し上げます。当院では、七月七日より八月までをお盆月間と定め、施餓鬼法要と塔婆建立により、皆さまの慰霊の志を先亡精霊へお届けさせていただきました。さらに、境内にはお盆飾りの一環としての笹飾りを用意し、祈願成就を願う参詣者さまより、多くの短冊を奉納いただきました。その願意は、絶えることなく世界のどこかで起こっている戦争や、米元大統領への狙撃事件などを反映してか、世界平和といった、世の無事を願うものから、家内安全や病気平癒、良縁成就、合格祈願、さらには亡き人への供養の気持ちを綴った個々の祈願まで多岐に亘ります。私どもはその願い事ひとつひとつに込められた皆さまの心境に想いを致し、お盆期間中の勤行にて謹んでご本尊さまにご回向させていただきました。 仏教では、願い事が叶うためには❶自分の力、❷仏さまの力、❸目に見えないものの力、この三力が肝要と説かれています。❶は、たとえば病気になったとき、治りたいという意思をもって病院に足を運び養生する、自分自身の力です。❷は、医者や薬、治療法といった、信頼し、おまかせできる他者の力です。そして❸は、家族や職場、近隣の人など、安心して養生できる環境を作り出してくれる、目に見えないさまざまなつながりの力、すなわち「おかげさま」の力です。 「咲いた花見て喜ぶならば、咲かせた根っこの恩を知れ」ー 私はいま五十六歳、両親も健在で、家族も無事でいてくれている、この一見なにごともない日々の喜びが、実は目に見えない無数の「おかげさま」の力によって与えられていることを、ようやく少しずつ実感し始めております。今年もまた秋のお彼岸がやって参ります。良き感謝のご供養に努めていただきたくご祈念申し上げます。合掌
南無大師遍照金剛
功徳院住職 松島龍戒
大きな地震で幕を開けた令和六年も、あっという間に半年を迎えようとしています。未だ復興の兆し見えない能登の皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。加齢とともに月日の経過が速まることを実感するようになりましたが、誤解を恐れずに言えば「あっという間だったね」と思えるのは、その間、特段の怖い目にも悲しいことにも出遭わずに、安泰な日々を過ごすことができた証とも言えるのではないでしょうか。当院では平素より募金箱を設置、浄財勧募を行っており、皆様からのお志を日本赤十字社を通じ被災地に送金しております。未だ水道も復旧してない地域もある現況に思いを致し、引き続きご協力をお願い申し上げます。
さて、お盆には亡き人への感謝の印に、お家にはお盆飾りに季節の野菜等をお供えし、お経やお香を捧げ、お墓にはお塔婆を建立します。尤も、人の心や家族の形は千人千通りですから、だれもが教科書どおりの供養や、等しい感謝の念を向けることはできません。中には親に感謝することができない、というかたもいるでしょう。が、感謝できない親の姿は、その人間性のほんの一面にすぎません。親とて人の子、現世での修行中、うまく子に伝えることができなかった親もいることでしょう。また、空海大師曰く、「賢者の説黙は時を待ち人を待つ」。良き親は、より深い理解を子に伝えようと、子が教えを素直に受け入れる準備ができているか、そのタイミングを見極め言葉を発し、時には沈黙も貫くという苦渋の選択すらしているのです。
お盆の季節、ありし日の「おかげさま」に感謝を向けて、良きご供養に努めていただきますようご案内申し上げます。
南無大師遍照金剛 功徳院 住職 松島龍戒
「一陽来復」
三十余年の歳月を要しても実感できないことがある。それを懺悔することの是非さえわからぬまま、寺に身を置いてきた未熟僧の私である。
「あたりまえは、あたりまえなどではない」
今朝も無事に目が覚め、事故に遭うこともなく、家族は決まった時間に帰ってくる――。
なにげない日常の「あたりまえ」が、目に見えない無数の奇跡の結果であると考える人は少ない。
蛇口から水が出る。ここにも水道管にトラブルひとつなかったという奇跡がある。生命の糧が常に与えられていること自体が奇跡なのだ。しかしながら、時に自然の営みはその奇跡を奪い去る。令和六年元旦、能登半島地震によって多くの命と希望が失われた。一寸先は闇と頭では理解しているが、そのあまりに無情な惨状が、自分の死や家族との別れを強く意識させた。この思いの大きさが、ボランティアで現地に入った平成七年の阪神淡路大震災、平成二十三年の東日本大震災の時にも増して大きいと感じるのは、年齢のせいだけでなく、守るべきものが増えたせいか。日々、死別を体験されたかたに接し、諸行無常を説く私自身が、日常の「あたりまえ」に安心を求めすぎていた。一休禅師の句「門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」を持戒せねばならない。
「抗がん剤の投与が始まり、髪が抜け始め、ようやく死を実感し、たばこをやめた」
以前見送った男性の言葉。享年三十三。この男性は、余命宣告され入院するまで「まだ大丈夫」と言い続けていた。せめてこの男性の胸中を借りて、「きっと多くの人が、あたりまえを実感できずにいる」と、自身の未熟さの慰めとさせてもらえぬものか――。
そんな愚考とは無縁に、今年もまた春のお彼岸はやってくる。せめて大切だった人に、ささやかな塔婆供養をささげ、普段思いを向けることの少ないご先祖に感謝し、明日もまた、多くの皆さまの安全無事と被災地能登の早期復興を祈りたい。
功徳院 住職 松島龍戒
登龍門(困難)から先に広がる、それぞれの未来(しあわせ)
令和六年辰年、輝かしい未来の幕開けです。辰年には仏教の守護神・龍が舞い降り、力強く、時に変化に柔軟に、私たちの未来を見守ってくださいます。
人生は四苦八苦、うまくいかないこと、辛いこと、悲しいことも多いかもしれません。そんなときは「登竜門」を心の糧としてみてはいかがでしょう。「登竜門」とは、急流を登り切った鯉が「龍」に成ったことから、成功や大願成就のために、困難を乗り越える大事を説いた故事です。言葉のイメージから、受験や試合、コンテストなど、一世一代の特別なことのように感じられるかもしれません。ですが、「苦楽」「良薬は口に苦し」「生みの苦しみ」などと言われますように、苦楽はいつも背中合わせ、楽しいことは苦しいことから生まれるように、私たちの日常は、すべてが幸せへの登竜門。日々の困難も、有り難い人生の糧として向き合うことができてこそ、その先に大きな幸せが訪れることでしょう。
功徳院では別紙ご案内の通り、節分星まつりを執り行います。多くの皆さまが楽しみにしてくださっている豆まきは、狭い境内での混乱が予想され、本年も中止と致しますが、法要の肝心である、本堂の厄除け護摩祈願へのご参列は再開致します。
四苦八苦という登竜門の先に、それぞれの幸せが広がる一年となりますよう、寺内一同心よりご祈念申し上げております。 合掌
功徳院住職 松島龍戒
残暑お見舞い申しあげます。
コロナの五類移行に伴い、今年の盂蘭盆施餓鬼法要は、これまでの大法要の形式から、ご家族ごとに本堂で読経する「個別供養」形式に変更して執り行い、三日間で約一〇〇組のご家族がご参列されました。その中には、今年初盆を迎えるかた、コロナ以前から施餓鬼法要にご参加されていたかた、おひとりでのご参加、あるいはご親族ら一〇名以上でのご参加など、さまざまなお姿がありました。それぞれに亡き人への深い思いをお持ちのことと拝察し、総本山・高野山からお招きした僧正様によるお加持とともに、一家族ずつ、懇ろにご読経をさせていただきました。
かつてはご自宅でのお盆供養が一般的でしたが、昨今、特に東京地方では、それが減少しつつあります。要因は、時代の変化やコロナの影響だけでなく、少子高齢化や住宅事情の変化、施設入居等によるお仏壇じまいの増加など、さまざまな背景があります。各ご家庭それぞれの供養の心をしっかりと受け止めることができるよう、引き続きよりよいお盆法要を厳修できるよう努めて参る所存です。
お盆が終わりますとすぐに秋のお彼岸が巡って参ります。お彼岸は、暑さ寒さや昼夜の時間の頃合いが良いことから、仏教では中道という「心の柔軟性」を学ぶ期間となっています。人生に四苦八苦あれど、中道の心で困難に向き合えば、時代や身心の変化に柔軟に適応でき、心穏やかな毎日を送ることができます。といって、人それぞれに、変わらず守りたい大切なものがおありのことでしょう。変わりゆくもの、守りたいもの、このバランスを上手にとることがまさに中道の精神なのです。
来るお彼岸、供養の思いは不動のままに、亡き人との良き心のふれあいとなれば幸いです。
また、月例行事のご参列も少しずつ再開します。別項にてご確認ください。手狭な境内ではありますが、みなさまのご参加をお待ちしております。 合掌
功徳院住職 松島龍戒
コロナの制限が緩和され、世の中が再び動きはじめています。
コロナは、多くの人の生命を奪い、雇用や経済、コミュニティの希薄化など、深刻な問題を引き起こしました。しかしそのいっぽうで、コロナをきっかけとして、オンラインなどテクノロジーの急速な普及が、教育や地域格差を縮め、柔軟な働きかたを生み出すなど、多くのメリットも生み出したのではないでしょうか。
まもなくお盆の季節です。お盆とは、亡くなった先祖やご家族を慰霊する伝統行事で、当院ではコロナ前までは、多くの皆さまが本堂に集まり、塔婆奉納する形式で大法要を執り行っておりました。コロナが落ち着きを見せてはいるものの、残念ながら今までのように、狭い境内に千人以上がお集まりいただくような形式での開催は難しい状況です。そこで本年は、コロナ後の社会通念や価値観の多様化に、より柔軟に応じるべく、別紙の通り、新しい形式でお盆の法要を開催することとなりました。ご不明の点やご意見などは遠慮なく寺務所にお寄せいただきたいと思います。
超高齢社会、さらには多死社会の到来とも言われる昨今、すがも平和霊苑の利用者も年々増え続けております。当院の限られた境内を効率よく生かし、できるだけご参詣の密集・混雑の緩和をはかりつつ、皆さまにとりましてより有意義なお盆供養を実現すべく尽力致します。何卒ご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
合掌
南無大師遍照金剛
南無三界万霊 功徳院住職 松島龍戒
日本三大霊場のひとつ高野山は、平安時代の名僧・弘法大師空海が開いた高野山真言宗の総本山で、平成十七年には世界遺産に登録、宗教宗派を超え、世界中の人々が訪れる真言密教の聖地です。
標高850メートル前後の山々に囲まれ、あたかも天空に浮かぶ広大な境内には、高野山のシンボル・高さ48・5mの根本大塔をはじめとする、無数の仏教建築や寺院が建ち並び、だれが呼んだか「日本のマチュピチュ」の比喩は、まさに言い得て妙です。
人々を引きつける高野山の最大の神秘は入定信仰、すなわち「弘法大師が、ここ高野山で今も生きて、人々の幸せを祈り続けてくださっている」という世界でも希有な信仰なのです。
私たち真言宗僧侶の多くは、この聖地に参籠修行して資格を取得するのですが、その修行の第一歩は、この入定信仰を信じることから始まります。が、寺に生まれ育ったわけでもなく、大学を出てまもなく、寝耳に水の心境で高野山に入山した当時の私には、恥ずかしながら、「今も生きていると言われても・・・」と、心の底から信じることはできませんでした。その気持ちに多少の変化が生じたのは、その数年後、さまざまなご縁を得て、三年間の高野山修行に励んでいたある日のことです。弘法大師の御廟「奥の院」にお参りした時、その前でお百度参りしているおばあさんをみかけました。その背中が丸くなっているのは、雪が積もる寒さのせいか、ご年齢のせいかわかりませんが、なにかお札のようなものを両手で抱き、素足で石畳の上をぴたぴたと、歩く音が聞こえてくるほどに、一心にお参りをされていました。そのお姿に接した時から私は、たしかにここにお大師さまがいらっしゃる。心からそう思えるようになりました。
大切なご家族など、先立たれたかたのお姿は直接見て、触れることはできません。が、日々の生活で出会う何かを通じ、間接的にその存在を信じられる瞬間がきっと、どなたにも訪れることと存じます。
来る春のお彼岸には、そんな亡き人のお姿を求め、お墓参りやお塔婆供養をしてみてはいかがでしょうか。
合掌
功徳院住職 松島龍戒
数年前のご法事でのことです。読経中、いつものように参列者に「ご焼香をどうぞ」と促したところ、施主さまの「あなたから先に焼香するんですよ。その次は○○君ね」そんな声がしましたので振り返りますと、普通、最初にご焼香してしかるべき故人の奥さま(施主)に先んじて、お孫さんたちが真っ先にご焼香されています。ご法事終了後、施主さまにそのことをお尋ねしますと、次のようなお答えが。「孫たちにとっては会ったこともないおじいさんの十七回忌。いずれ我が家の法事を担っていくのはこの子たちですから、私が死んだあともおじいさんの供養を大切に続けてもらえるように、法事の主役を孫たちにしてるんです」
一般的な仏事作法としては、正しいと言えないかもしれません。
しかし、コロナが追い打ちをかけている、昨今の仏事縮小傾向を目の当たりにする中、法事を末永く大切にしたいと願う、このご家庭にとっての「智慧」を見たような気がしました。
令和五年の護り本尊は文殊菩薩。
「文殊の智慧」といいますが、これは知識や情報に頼りすぎない、慈悲~やさしさ~を伴うもの。その実践のために、文殊菩薩は「利剣」を手に戒めています。この利剣で断ち切るべきは、世間の目やしがらみ、ねたみ、かたよった考えから起こる、柔軟さを欠いた心です。コロナ以降、世の中は急速に変わりつつあります。みなさまそれぞれにとっての「文殊の智慧」で、よりよい年をお過ごしいただきますようご祈念申し上げます。
合掌
功徳院住職 松島龍戒
先日、和歌山県の高野山にお参りしました。
高野山とは、平安時代のはじめに弘法大師・空海さまが開いた高野山真言宗の祖山です。ここには、『空海さまが今なお生きて座禅瞑想し、人々の幸せを祈り続けてくださっている』そんな信仰があります。
仏教の開祖、お釈迦さまでさえ入滅し、荼毘に付されたと伝承されておりますが、なぜ空海さまに限って、そんな特別な信仰が生まれたのでしょうか。これには『毛は伸び放題、衣も朽ち果て、座禅している空海さまに直接触れた』という高僧の記録がきっかけになった、など諸説ありますが、私は、空海さまの底知れぬ人間的魅力、心の深さにその理由があると感じています。
それを伺い知るひとつが、永遠の住処として定めた高野山奥の院に「お入りになる」直前に遺された次のお言葉です。「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、我が願いも尽きなむ(この世の、生きとし生けるすべてが救われないかぎり、私の祈りは永遠に尽きることがないのです)」なんと、途方もなく大きなご請願でしょうか。
それゆえに人々はいつしか、「高野山に登れば、空海さんに会える」そう信じはじめ、今もなお、宗教宗派、国の内外を問わず、「生きた」空海さまにお会いするために、人々が高野山に訪れているのだと思います。
人はだれも、この世とお別れするその時が近づくにつれ、遺してゆく人への思いを、強くされるのではないでしょうか。それは空海さまのような偉大な人に限らず、たとえば、普通の親が子へ遺す気持ちであれ、空海さまに負けないくらい深く、強く、大きい。私はそう信じています。そしてその思いは、きっとこの世のどこかに、形となり、香りとなりどこかに残っているはずです。
来る秋のお彼岸には、亡き人の「思いの痕跡」を探し、お墓参りやお塔婆供養をしみてはいかがでしょうか。
合掌
功徳院住職 松島龍戒